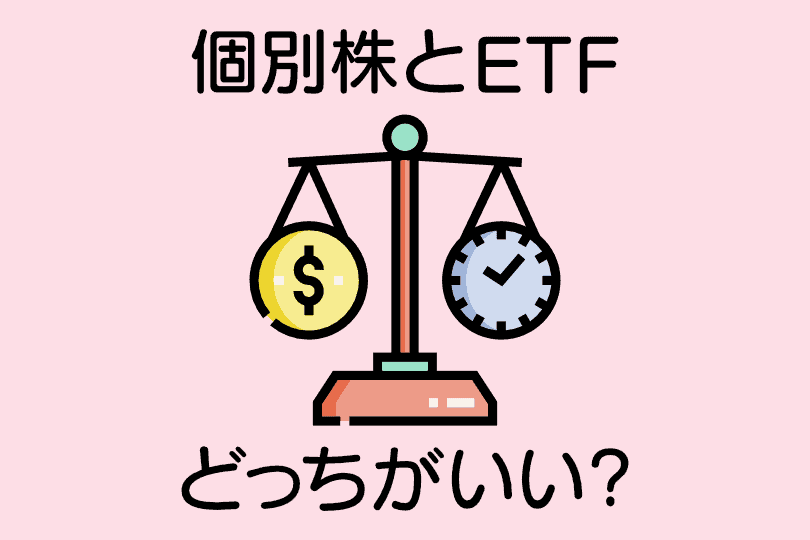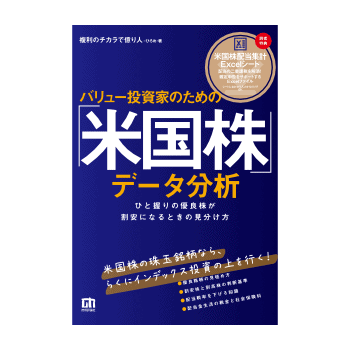読者さん
個別株とETFどっちがいいんだろう?
米国株に投資するとき、個別株とETFどっちがいいか迷いますよね。
そこで今回は、個別株かETFかを選ぶときに考えたい重要チェックポイントをお伝えします。
ここに出てくるチェックポイントを考えるだけで、あなたに合った答えが自然と出てくるはずです。
筆者の自己紹介をカンタンにしておくと、投資歴8年で技術評論社から米国株の書籍を出版しています。
生涯リターンの最大化が目的
資産運用の目的は生涯リターンの最大化です。生涯リターンとは、人が一生のうちで得る資産運用のリターン合計額のことです。
- 投資資金×年率リターン×運用年数-税金
この生涯リターンを決める要素のうち、個人がコントロールできるのは「投資資金」と「運用年数」の2つだけになります。
つまり先に結論に結論を申し上げると「運用年数」と「投資資金」が多くなる選択が正解というわけです。
こんなこと書くと「え?年率リターンはコントロールできないの?」と思う人がいるかもしれません。
そこでまずは、年率リターンについて考えてみましょう。
クリックできる目次
年率リターンの長期比較
年率リターンは制御不能?
株式投資は高いリターンの銘柄に投資することが重要だと考える人が多くいらっしゃいます。私自身もそのように考えていた時期がありました。
ですが残念なことに、将来何%のリターンが確実に得られる銘柄というのは誰にも分かりません。
株式投資の世界では、これまで何年もインデックスを上回る素晴らしいリターンを上げてきた個別株が、ある日を境に低迷することが往々にしてあります。
反対に、これまで何年も低迷していた割安株が急に上昇してインデックスのリターンを上回るようになることだって起こります。
要するに、過去のリターンが未来も続く保証は、どこにもないわけですね。
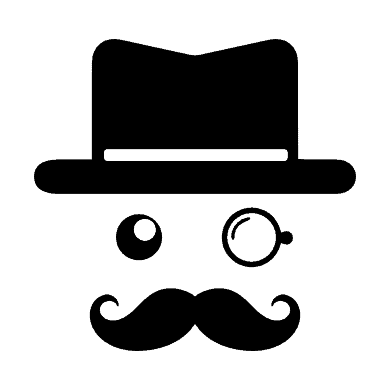
配当きぞくん
この先のリターン比較を見てもらうと予測できないことがよく分かるのじゃ。
個別株は優良株への投資が大前提
個別株にはバリュー投資、グロース株投資、高配当株投資など様々な手法があります。ただ、どの手法にも共通する必須の条件は優良株に投資し続けることです。
普通の人でも優良株に投資し続けることは可能です。具体的な方法はリンク先の記事で解説しているのでまだ読んでない方は見てみてください。
Check 【優良株の探し方】普通の人でも優良銘柄が見分けられるシンプル法則
こちらを読むことで次のリターン比較で取り上げられてる個別株の共通点が分かります。
年率リターンの比較条件
ここからは、iシェアーズ・コア S&P 500 ETF(IVV)と優良米国株のリターンを比較します。
S&P500指数にIVVを選んだ理由は、設定日が2000年5月だったからです。
S&P500のETFといえばVOOも有名ですが、設定日が2010年9月と歴史が浅く株価が遡れないのでIVVを採用しました。
【比較条件】
- 配当再投資はナシ
- 税金/手数料は考慮せずに比較
- 年初を基準に年末のリターンを算出
- 年率リターン=株価上昇率+配当(分配)利回り
配当(分配)利回り=年間配当/年初株価
「年率リターン=株価上昇率+配当(分配)金」で、リターン差がマイナスだとIVVが勝利、プラスだと個別株が勝利した年になります。
コカ・コーラ(KO)
| 暦年 | KO | IVV | リターン差 |
|---|---|---|---|
| 2010年 | +18.39% | +13.05% | +5.34% |
| 2011年 | +10.17% | +0.82% | +9.35% |
| 2012年 | +6.27% | +14.15% | -7.88% |
| 2013年 | +12.85% | +28.89% | -16.05% |
| 2014年 | +6.84% | +14.48% | -7.64% |
| 2015年 | +5.08% | +1.25% | +3.82% |
| 2016年 | +1.08% | +13.62% | -12.54% |
| 2017年 | +13.30% | +20.73% | -7.43% |
| 2018年 | +7.40% | -4.47% | +11.87% |
| 2019年 | +21.35% | +30.97% | -9.62% |
| 2020年 | +2.71% | +16.85% | -14.14% |
| 2021年 | +15.41% | +30.39% | -14.98% |
| 2022年 | +10.24% | -18.60% | +28.83% |
| 2023年 | -3.46% | +26.66% | -30.13% |
| 2024年 | +7.32% | +25.57% | -18.25% |
| 平均 | +9.00% | +14.29% | -5.30% |
コカ・コーラは過去15年で5勝10敗(勝率33%)、トータルリターンの差は、年率平均5.30%インデックスを下回っています。
Check コカ・コーラ(KO)銘柄分析:株価指標と配当利回りから導いた割安な株価の条件
マクドナルド(MCD)
| 暦年 | MCD | IVV | リターン差 |
|---|---|---|---|
| 2010年 | +25.87% | +13.05% | +12.81% |
| 2011年 | +34.28% | +0.82% | +33.46% |
| 2012年 | -7.85% | +14.15% | -22.00% |
| 2013年 | +11.13% | +28.89% | -17.76% |
| 2014年 | +0.59% | +14.48% | -13.89% |
| 2015年 | +30.37% | +1.25% | +29.11% |
| 2016年 | +6.59% | +13.62% | -7.03% |
| 2017年 | +47.09% | +20.73% | +26.36% |
| 2018年 | +4.93% | -4.47% | +9.40% |
| 2019年 | +14.93% | +30.97% | -16.04% |
| 2020年 | +9.38% | +16.85% | -7.47% |
| 2021年 | +30.02% | +30.39% | -0.37% |
| 2022年 | +0.23% | -18.60% | +18.82% |
| 2023年 | +14.53% | +26.66% | -12.13% |
| 2024年 | -0.12% | +25.57% | -25.70% |
| 平均 | +14.80% | +14.29% | +0.51% |
マクドナルドは過去15年で6勝9敗(勝率40%)、トータルリターンの差は、年率平均0.51%インデックスを上回っています。
Check 【MCD】マクドナルド銘柄分析:株価指標と配当利回りから導いた割安な株価の条件
ジョンソン&ジョンソン(JNJ)
| 暦年 | JNJ | IVV | リターン差 |
|---|---|---|---|
| 2010年 | -1.11% | +13.05% | -14.17% |
| 2011年 | +7.98% | +0.82% | +7.16% |
| 2012年 | +10.05% | +14.15% | -4.11% |
| 2013年 | +32.95% | +28.89% | +4.05% |
| 2014年 | +17.91% | +14.48% | +3.43% |
| 2015年 | +1.10% | +1.25% | -0.15% |
| 2016年 | +17.79% | +13.62% | +4.17% |
| 2017年 | +23.48% | +20.73% | +2.75% |
| 2018年 | -4.77% | -4.47% | +0.30% |
| 2019年 | +17.12% | +30.97% | -13.85% |
| 2020年 | +10.54% | +16.85% | -6.30% |
| 2021年 | +11.99% | +30.39% | -18.40% |
| 2022年 | +5.57% | -18.60% | +24.17% |
| 2023年 | -9.40% | +26.66% | -36.06% |
| 2024年 | -6.59% | +25.57% | -32.16% |
| 平均 | +8.97% | +14.29% | -5.32% |
ジョンソン&ジョンソンは過去15年で7勝8敗(勝率46%)、トータルリターンの差は、年率平均5.32%インデックスを下回っています。
Check ジョンソン&ジョンソン(JNJ)銘柄分析:株価指標と配当利回りから導いた割安な株価の条件
P&G(PG)
| 暦年 | PG | IVV | リターン差 |
|---|---|---|---|
| 2010年 | +8.34% | +13.05% | -4.72% |
| 2011年 | +6.17% | +0.82% | +5.35% |
| 2012年 | +4.89% | +14.15% | -9.26% |
| 2013年 | +20.73% | +28.89% | -8.16% |
| 2014年 | +16.24% | +14.48% | +1.76% |
| 2015年 | -9.29% | +1.25% | -10.54% |
| 2016年 | +10.69% | +13.62% | -2.93% |
| 2017年 | +12.37% | +20.73% | -8.36% |
| 2018年 | +4.54% | -4.47% | +9.00% |
| 2019年 | +40.07% | +30.97% | +9.10% |
| 2020年 | +15.27% | +16.85% | -1.58% |
| 2021年 | +21.16% | +30.39% | -9.23% |
| 2022年 | -4.75% | -18.60% | +13.85% |
| 2023年 | +0.85% | +26.66% | -27.52% |
| 2024年 | +15.38% | +25.57% | -10.20% |
| 平均 | +10.73% | +14.29% | -3.56% |
P&Gは過去15年で5勝10敗(勝率33%)、トータルリターンの差は、年率平均3.56%インデックスに負けています。
Check P&G(PG)銘柄分析:株価指標と配当利回りから導いた割安な株価の条件
ウォルマート(WMT)
| 暦年 | WMT | IVV | リターン差 |
|---|---|---|---|
| 2010年 | +1.68% | +13.05% | -11.38% |
| 2011年 | +12.19% | +0.82% | +11.37% |
| 2012年 | +15.71% | +14.15% | +1.56% |
| 2013年 | +16.36% | +28.89% | -12.53% |
| 2014年 | +11.29% | +14.48% | -3.19% |
| 2015年 | -26.36% | +1.25% | -27.61% |
| 2016年 | +15.70% | +13.62% | +2.08% |
| 2017年 | +46.79% | +20.73% | +26.06% |
| 2018年 | -3.40% | -4.47% | +1.07% |
| 2019年 | +29.59% | +30.97% | -1.37% |
| 2020年 | +23.00% | +16.85% | +6.15% |
| 2021年 | +0.25% | +30.39% | -30.13% |
| 2022年 | -0.44% | -18.60% | +18.15% |
| 2023年 | +11.36% | +26.66% | -15.30% |
| 2024年 | +71.71% | +25.57% | +46.14% |
| 平均 | +15.03% | +14.29% | +0.74% |
ウォルマートは過去15年で8勝7敗(勝率53%)、トータルリターンの差は、年率平均0.74%インデックスに買っています。
Check ウォルマート(WMT)銘柄分析:株価指標と配当利回りから導いた割安な株価の条件
アイ・ビー・エム(IBM)
| 暦年 | IBM | IVV | リターン差 |
|---|---|---|---|
| 2010年 | +12.78% | +13.05% | -0.27% |
| 2011年 | +26.74% | +0.82% | +25.92% |
| 2012年 | +4.67% | +14.15% | -9.48% |
| 2013年 | -2.50% | +28.89% | -31.39% |
| 2014年 | -11.12% | +14.48% | -25.60% |
| 2015年 | -11.85% | +1.25% | -13.10% |
| 2016年 | +26.34% | +13.62% | +12.72% |
| 2017年 | -4.54% | +20.73% | -25.27% |
| 2018年 | -22.09% | -4.47% | -17.63% |
| 2019年 | +22.19% | +30.97% | -8.77% |
| 2020年 | -2.01% | +16.85% | -18.86% |
| 2021年 | +18.44% | +30.39% | -11.95% |
| 2022年 | +8.41% | -18.60% | +27.01% |
| 2023年 | +20.23% | +26.66% | -6.44% |
| 2024年 | +40.25% | +25.57% | +14.68% |
| 平均 | +8.40% | +14.29% | -5.90% |
IBMは過去15年で4勝11敗(勝率26%)、トータルリターンの差は、年率平均5.90%インデックスに負けています。
Check IBM銘柄分析:株価指標と配当利回りから導いた割安な株価の条件
エクソンモービル(XOM)
| 暦年 | XOM | IVV | リターン差 |
|---|---|---|---|
| 2010年 | +8.26% | +13.05% | -4.80% |
| 2011年 | +16.18% | +0.82% | +15.36% |
| 2012年 | +3.17% | +14.15% | -10.98% |
| 2013年 | +16.85% | +28.89% | -12.04% |
| 2014年 | -4.61% | +14.48% | -19.09% |
| 2015年 | -12.93% | +1.25% | -14.18% |
| 2016年 | +20.37% | +13.62% | +6.75% |
| 2017年 | -4.61% | +20.73% | -25.34% |
| 2018年 | -16.01% | -4.47% | -11.54% |
| 2019年 | +5.05% | +30.97% | -25.92% |
| 2020年 | -36.95% | +16.85% | -53.80% |
| 2021年 | +55.86% | +30.39% | +25.47% |
| 2022年 | +79.18% | -18.60% | +97.78% |
| 2023年 | -2.68% | +26.66% | -29.34% |
| 2024年 | +8.84% | +25.57% | -16.73% |
| 平均 | +9.07% | +14.29% | -5.23% |
エクソンモービルは過去15年で4勝11敗(勝率26%)、トータルリターンの差は、年率平均5.23%インデックスに負けています。
Check エクソンモービル(XOM)銘柄分析:株価指標と配当利回りから導いた割安な株価の条件
運用年数を伸ばすポイント
優良株でも勝率は40%~60%
ここまでの結果から分かるように長期リターンでインデックスを上回る個別株でも指数を上回る年は多くて60%しかありません。
個別株は15年のうち6年はインデックスを下回っても優良株である限り保有し続ける必要があるわけです。
何かあるたびすぐ売ってしまうと、保有期間が短くなって最終的な生涯リターンが下がってしまいます。
これは個別株に限らずインデックスも同じで、S&P500指数が下がり続けたとしても含み損を気にせず淡々と積み立て続けることが重要になります。
有事の際、配当なしでも保有できるか
予期せぬ失業やライフイベントなどで予定外の支出が発生したときに、投資資金の現金化に迫られるリスクがあります。
そしてこのような状況に追い込まれるときは、往々にして不況のときがほとんどです。
- 仕事の収入減と株価暴落が同時に発生ETF分配金が減配されて利回りが減少
具体的なリスクについての説明は下記のページに書いてあります。ここに書かれているリスクを認識しているかいないかの差は大きいと思いますね。
Check 経験者が感じたインデックス投資の弱点とデメリット4選を具体的に解説します
不況になると当然のごとく株価は暴落します。株価が暴落した状況で売却することになれば、かなりの安値で売り払うことになってしまいます。
もし今後何年も含み損を抱えることになったとしても、個別株の配当だけでやり繰りすることができれば株を売らなくて済みます。
結果的にインデックスのリターンが高くなったとしても、不況を乗り越えて個別株を保有できた方が運用年数が長くなって生涯リターンも高くなるわけです。
私が個別株投資を選択している理由は、まさしくこの点にあります。
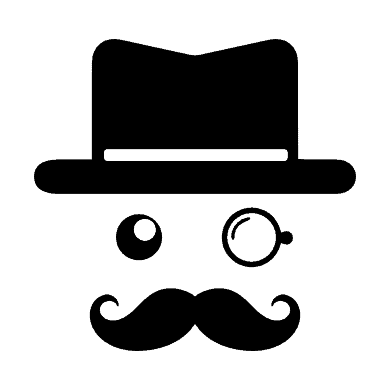
配当きぞくん
具体的なシミュレーションは下のページに書いてあるぞい。
Check アーリーリタイア後の生活費と副収入を計算したら意外にも手が届く金額だった
投資資金の多さも大切
投資資金が多ければ多いほど、プラスリターンになったときの運用益は大きくなります。
コントロールできない年率リターンを気にするより、投資資金を多くすることに集中する方が運用益の最大化に繋がるわけです。
リスク許容度の高さで考える
投資できる金額が多い方を選ぶというのは、リスク許容度の高い投資先を選ぶことと同じです。
もし株式市場の大暴落が発生したら長期的に含み損を抱えることになりますよね。このような状況でも保有できる金額が多いのはどっちなのかを考えます。
やはり私は25年連続増配中の割安高配当株の方がインデックスより保有金額を多くできるので、個別株を選びました。
税金の種類
税金には売却益にかかる税金と配当(分配)金にかかる税金の2種類があります。特定口座とNISA口座で変わってくるので、それぞれについて見てみましょう。
特定口座
売却益にかかる税率は一律20.315%でシンプルです。一方で、配当(分配)金にかかる税金は少し複雑で、個人の年収によっても最適解が変化します。
【特定口座の税金】
- 売却益:一律20.315%
- 配当(分配)金:選択する課税方式によって異なる
配当(分配)金にかかる税金については、解説ページのリンクを以下にまとめておきますね。
年間損益マイナスにしたときのリスク
特定口座で年間損益がマイナスになると税制上デメリットがあります。
年間損益がマイナスのときは確定申告しないと翌年以降に損失を繰り越せなくなるのです。
仮に確定申告して損失を繰り越したとしても、3年が過ぎると損失が繰り越せなくなってしまいます。
具体的な説明として、国税庁ホームページでは次のように書かれています。
上場株式等の譲渡損失の金額については、一定の要件を満たす場合に限りその譲渡損失の金額が生じた年の翌年以後3年間にわたって上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得等の金額から繰越控除できます。(一般株式等に係る譲渡所得等の金額から繰越控除することはできません。)
この控除をするには、上場株式等に係る譲渡損失の金額が生じた年分の所得税について一定の書類を添付した確定申告書を提出するとともに、その後の年において、連続して一定の書類を添付した確定申告書を提出する必要があります。
No.1465 株式等の譲渡損失(赤字)の取扱い
損益通算しやすいのは個別株
特定口座で含み損を抱えたとき現金化しやすいのは個別株です。ここでいう個別株は、25年以上連続増配中の割安高配当株を指しています。
個別株の方が含み損のとき現金化しやすい理由は次の2つあります。
- 配当と売却損を損益通算できる
- 含み益の銘柄と含み損の銘柄を損益通算できる
25年以上連続増配中の個別株は不況でも増配を続けることがほとんどです。そのため、きちんと複数銘柄に分散投資できていれば株価暴落しても年間受取配当額は増え続けます。
対して、S&P500インデックスETFの分配金は不況入りするとほぼ確実に減配されてきた実績があります。
受け取り配当金が多ければ多いほど保有株を損出しできる量も増えるので、いざというとき現金化しやすいのは個別株になります。
また、ETFは分散投資する必要がないので他の銘柄と損益通算できる機会は非常に少なくなります。
個別株なら12~18銘柄に分散するのが基本なので、含み益になった銘柄と含み損の銘柄を損益通算できる場面は多いです。
過去の歴史を振り返るとS&P500インデックスが暴落前の最高値を更新するのにかかった最長期間は25年です。
この記録は世界大恐慌のときのもので、暴落前の最高値を更新するのに25年(1929年8月~1954年8月)かかりました。
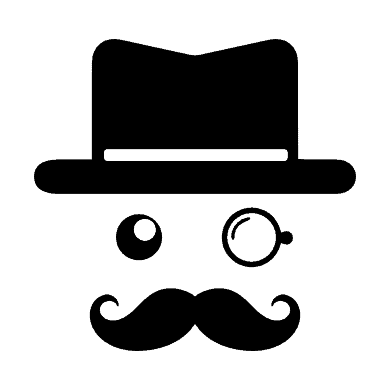
配当きぞくん
長期で含み損を抱えるリスクも考慮して選択すべきじゃな。
NISA口座
NISA口座の保有株は売却益にかかる税金がタダになります。
配当(分配)金にかかる税金も基本的にかからないのですが、外国所得税だけは例外として扱われます。
米国株の外国所得税は10%なので、NISA口座で受け取る配当分配金には10%の税率がかかることになるのです。
【NISA口座の税金】
- 売却益:一律0%
- 配当(分配)金:外国所得税10%
個別株でもETFでも税率は一緒
個別株とETFで税金の差が出る要素は、売却益と配当(分配)金の比率になります。
個別株は連続増配株を保有する前提なので、ETFの売却益より配当でリターンを受け取る割合の方が多くなります。
対して、ETFは分配金利回りが低く減配することもあるので、基本的にリターンの大部分は売却益で受け取ることになります。
よって、配当で受け取った方が税率を低くできるのであれば個別株、売却益で受け取った方が税率を低くできるのであればETFが有利になります。
チェックポイントまとめ
個別株は25年以上連続増配中の割安高配当株、ETFはS&P500指数への投資を前提にすると、それぞれに向いている人の特徴は次のようになります。
- 安定収入が続くか分からない
- 増やすより減らすリスクを抑えたい
- 配当がなくても問題ない
- 管理に時間をかけたくない
生涯リターンの最大化には「運用年数」と「投資資金」をどれだけ多くできるかがポイントになります。
要するに尽き詰めて考えると、できるだけ多くの資金を長く運用できる選択が正解になるわけですね。
米国株の本を書きました!中身をブログで無料公開しています。書店で買えるガチの書籍が無料で読めるようになっています。
資産運用の知識